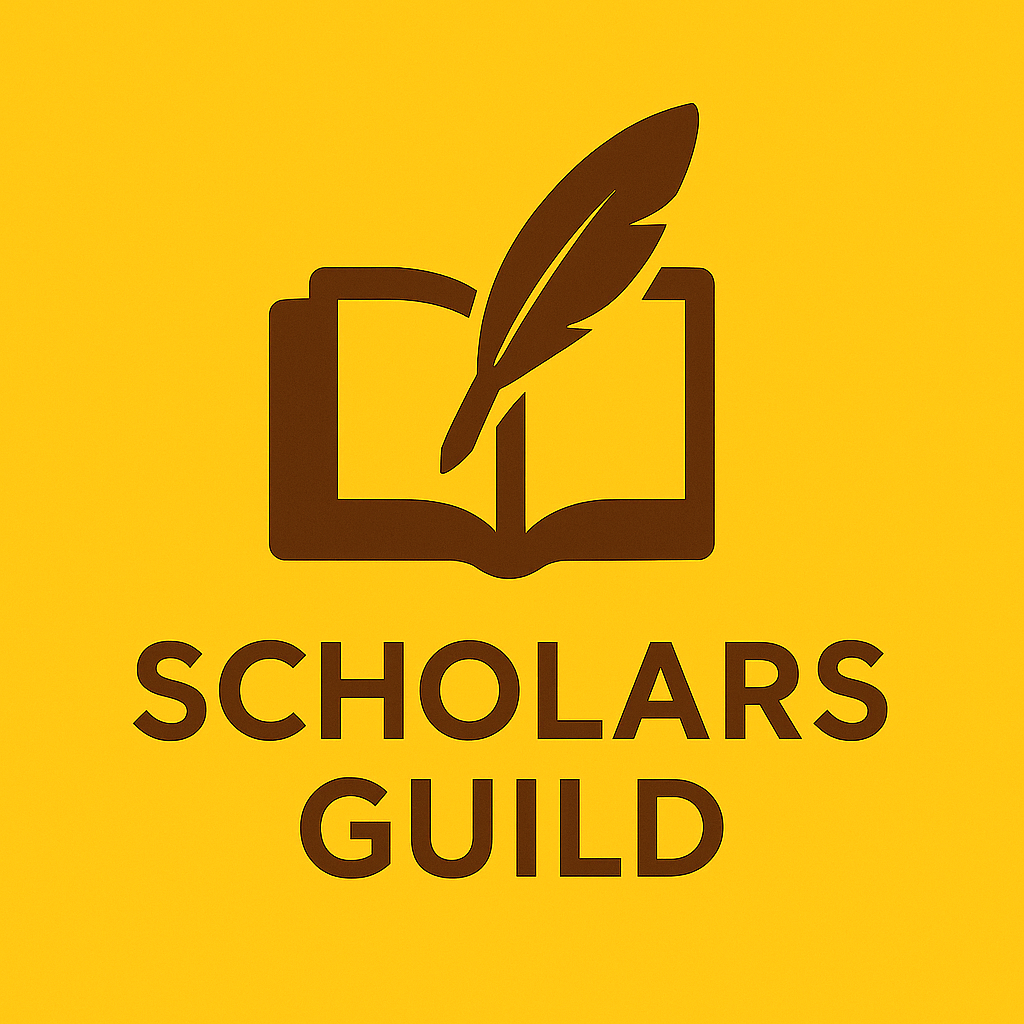教育・社会接続推進協議会
スカラーズ・ギルド(教育・社会接続推進協議会)は、学術界と社会を結びつける架け橋として活動する有志の協議会です。
本協議会は、高等教育現場で培われた知見や研究成果を社会課題の解決へと還元し、また現場のニーズを教育・研究へとフィードバックする双方向の循環を促進します。
具体的には、
- 高等教育・専門教育におけるカリキュラムと地域産業・行政との連携強化
- 学生や若手研究者の社会参画機会の創出
- 教育育政策・制度設計に関する調査・提言
- 公開講座・ワークショップ等を通じた一般市民との知識共有
- 知的資源を活用したテスト事業や実習事業・・・など
様々な知的接続事業を展開しています。
学問を閉じた塔から解き放ち、教育を通じて社会全体の知的基盤を高めること。 大学にできない生きた知的生産活動を社会へーーーーーそれがスカラーズ・ギルドの使命です。
1学知の公共性と社会実装に関する学際研究会
- テーマ例
- 哲学・社会学・教育学・科学論の視点から「知の公共性とは何か」を再検討し、実社会での知の活用(エビデンス政策、教育現場、メディア等)を具体的に検討。
- 連携候補学会
- 公共政策学会・科学技術社会論学会・教育社会学会など
2科学技術・医療の倫理と市民社会に関する研究フォーラム
- テーマ例
- ゲノム編集、AI医療、気候工学、パンデミック対応などの新技術に対する倫理的枠組みと合意形成
- アウトカム
- 市民フォーラムや意見書作成
- 連携候補学会
- 生命倫理学会・日本科学哲学会など
3日本の高等教育政策と国際化に関する批判的検討会
- 議題例
-
- 教員養成制度改革と学力格差
- 地域大学の役割と再編問題
- 外国人留学生政策の展望と課題
- 背景
- 大学政策・学術行政にかかわる知見の還元
- 協力先候補学会
- 大学行政学会・高等教育学会・日本比較教育学会など
4地域文化と記憶・歴史の継承をめぐる研究プロジェクト
- 内容
- 地域アーカイブ、地方史の掘り起こし、民俗知の継承、都市史と公共空間の再解釈。
- 学術的意義
- 人文学と地域再生を接続
- 活動形態
- 調査研究・口述史の記録・公開講座
- 関連学会
- 歴史学会・日本民俗学会・文化資源学会・公共人類学など
5「退職研究者の知の再活用」自体を研究対象としたメタ研究会
- テーマ
- 知識のライフサイクルと再配置、経験知の制度化、オルタナティブな学術キャリアの構築。
- アウトプット
- 学会発表、査読論文、公的政策への提言
- 関連領域
- 教育社会学・知識社会論・研究開発政策学
6ポスト成長社会における学問の役割と再定義を考える連続セミナー
- 内容
-
- 「脱成長」と学問の再編
- 地域知・実践知とアカデミズムの交差
- 学問的専門性の「社会的役割」の再設計
- 視座
- 経済成長に依存しない社会における「知的生産」の意味を問う
- 文脈
- 環境人文学・持続可能性科学との接点
7アジア圏における「知の循環」比較研究プロジェクト
- 視点
- 日本・韓国・中国・東南アジアの高等教育、研究制度、公共知の形成・移動
- 目的
- 地域的文脈の中での知的生産モデルを再評価
- 方法
- 比較教育学、知識社会学、制度論
8学術日本語運用能力に係る定義および能力評価基準策定委員会
- 目的
- 高等教育・研究活動において求められる「学術的日本語運用能力(Academic Japanese)」の定義を再検討し、それに基づく評価基準・測定方法を策定する。外国人留学生のみならず、日本人学生・研究者にとっても必要不可欠な「知的な言語能力」としての日本語を捉え直すことが目的である。
- 背景と問題意識
-
- 昨今、日本人学生・若手研究者の「国語力(=論理的読解力・記述力・語彙力・言語的構成力)」の劣化が深刻な教育課題として顕在化している。
- 同時に、日本語で研究・教育を行う外国人留学生の急増により、「研究遂行に足る日本語能力」の可視化と育成が急務となっている。
- しかし現状では、JLPT(日本語能力試験)や大学入試国語では、論理展開・引用・批判的思考・学術表現スタイルなどを体系的に測定できていない。
- 「学術日本語」は、もはや外国人だけの課題ではなく、母語話者も含めた全学生・研究者にとっての基盤的能力として再定義されるべきである。
- 検討課題
-
- 学術日本語の構成要素(要約・引用・論述・語彙の適格性・スタイル・文献の取り扱い等)の明確化
- 評価ルーブリックと参照枠(たとえばCEFR-J、JFS、Bloomのタキソノミーとの連関)
- 書き言葉能力だけでなく、口頭発表・ディスカッション・インタビュー等の対人的表現能力も含めた測定枠の整備
- 外国人・日本人の別なく「高等教育・研究における言語運用能力の最小基準」として機能する枠組みの提示
- 想定される成果
-
- 「AJPT(Academic Japanese Proficiency Test)」等、実務に直結する学術日本語能力試験のモデル設計
- 各大学のアカデミック・スキル育成講座や教養教育科目に対するカリキュラム設計の基盤提供
- 留学生・帰国生・日本人学生を問わず、多様な学習者に対応した汎用的評価基準の策定
- 将来的には、研究公用語としての日本語の維持・発展に寄与
- 協議先候補
-
- 日本語教育学会、大学日本語教育学会、日本語学会
- 国立国語研究所、文部科学省高等教育局、各大学の留学生センター・教育開発センター
- 国際共通参照枠(CEFR)、アカデミック・ライティングセンター等